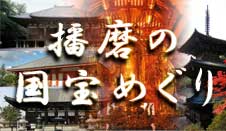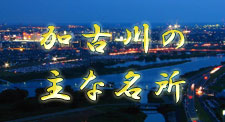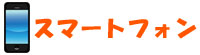|
|
お客様のご希望に合わせたコースをご提案!
|
|
 |
【場所】 【築城主】櫛橋則伊 現在、本丸跡は観音寺の境内となり、二の丸跡は志方小学校になっています。また、黒田官兵衛の妻・光(てる)の実家です。官兵衛は生涯 を通して光(てる)ただ一人を愛したと言われています。 |
西条城跡 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市八幡町中西条 【築城主】赤松則村 築城年代は定かではありません。加古川南岸の標高85.1mの城山に築かれていたといわれています。城山の東側の集落から登城道があります。 |
 |
【場所】兵庫県加古川市東神吉町神吉 【築城主】赤松範次 現在、城跡は中の丸が法性山常楽寺、西の丸が真宗寺となっています。常楽寺の本堂裏にある墓地には城主神吉頼定の墓があります。 わがまち加古川60選のNo.48です。 |
加古川城跡 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町本町 【築城主】糟屋有教 加古川城播磨国印南郡加古川村(現:加古川町本町)にあった平城です。現在、城跡は称名寺となっています。 平家追討の戦功により、糟谷有数が源頼朝よりこの地を与えられ、承久の乱後(寿永3年(1184年))に築城されました。 現在、城跡としての遺構はほとんどありません。 |
長楽寺 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市志方町永室853-1 【本尊】造地蔵菩薩半跏像(国重要文化財) 2011年の台風12号で甚大な被害を受けました。本堂、阿弥陀堂は土砂により全壊しましたが、重要文化財である「木造地蔵菩薩半跏像」は無事です。 「谷の子安地蔵」として安産祈願に多くの人が訪れています。 |
 |
【場所】兵庫県加古川市野口町野口465 【本尊】阿弥陀如来 称名念仏の創始者である教信によって開基されました。念仏を唱えながら仏の教えを説き、お百姓の手伝いをし、わらじを作って貧しい人に与えたり、 旅をするお年寄りの荷物を運んだりして、大勢の人を助けたことから「荷送り上人」や「阿弥陀丸」とも呼ばれました。 樹齢100年近い老木をはじめとする約60本のソメイヨシノで知られる、桜の名所です。 |
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町北在家424 【国宝】本堂・太子堂 聖徳太子開基伝承をもつ寺院の1つで、太子建立七大寺の一つともいうが、 創建の詳しい事情は不明である。平安時代建築の太子堂(国宝)をはじめ、 「あいたた観音」など多くの文化財を有し、「西の法隆寺」とも称されている播磨地方有数の古寺である。 |
横蔵寺 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市平岡町新在家900 【本尊】釈迦如来 白雉年間(西暦653年)法道仙人により開基。 光孝天皇の時代に祈願所となり、宇多天皇が譲位の後、出家して寛平法皇となってからは、法皇の潜邸として栄えました。 観音堂に安置される十一面千手千眼観音像(鎌倉時代)は秘仏で、25年おきに開帳されます。 |
円照寺 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市志方町廣尾1029 【本尊】阿弥陀如来像 花の寺として知られ、3月から11月にかけてクリスマスローズ・椿・ユキヤナギ・ ライラック、アジサイ・ノウゼンカズラ、酔芙蓉などの花が咲き乱れます。 境内には明応7年(1498)の年号が刻まれた市指定文化財の銅鐘もあります。 |
志方八幡宮 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市志方町志方町301-2 【創祀時期】天永2年 播磨三社八幡の一つです。祭神は、応神天皇、神功皇后、玉依比売命(たまよりひめみこと)です。志方荘30ヶ村を鎮守したといわれています。 |
平之荘神社 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市平荘町山角478 【創祀時期】和銅6年 明治初年の神仏分離まで、西隣の報恩寺の鎮守神でした。 祭神は建速素盞鳴尊外6柱です。鎌倉・室町時代の石造遺品が多く、 県指定重要文化財の石造十三重塔、市内最古の石造五輪塔などがあります。 |
 |
【場所】兵庫県加古川市八幡町野村580 【創祀時期】天平感宝元年め 祭神は息長足媛命、品陀別命、仲姫命です。 “宗佐の厄神さん”と呼ばれ、毎年2月18・19日には、各地から数万人の参拝者が厄払いに訪れる厄除大祭が開催されます。 |
泊神社 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町木村658 【祭神】天照大神・少彦名神・国懸大神 神代に伊勢神宮の御神体の一つである御鏡がここに泊まり、 アオキの木を檍原泊大明神として祀ったのが泊神社の始まりとされています。 宮本伊織ゆかりの神社で田原氏(宮本伊織の実家)の氏神です。 |
 |
【場所】兵庫県加古川市尾上町長田518 【祭神】住吉大明神 神社にある尾上の鐘とも呼ばれる梵鐘は国の重要文化財に指定されています。 境内には、能の作品の一つ「高砂」にも詠まれ天然記念物であった尾上の松が あることでも有名でです。現在は五代目となります。 |
日岡神社 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町1755 【祭神】天伊佐佐比古命 第12代景行天皇の皇后、播磨稲日大郎姫命が難産だった事から、 祭神の天伊佐佐比古命が安産祈願したとする社伝に基づき、安産の神として東播磨地域で広く信仰されています。 |
野口神社 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市野口町326 【祭神】大山咋命 比叡山延暦寺の守護神日吉大社の分霊を祭る由緒ある神社です。 神社の西にある教信寺は延暦寺の末寺であることから深いつながりがあります。 |
浜の宮神社(浜宮天神社) |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市尾上町口里770 【祭神】菅原道真公 学問の神様で有名な「菅原道真公」由来の神社のです。 「我を信ずる輩は諸の悪事災難風波の難を救はん」との御神託を伝え、 学業成就、縁結び、家業繁栄、交通安全、の神様と仰がれています。 |
 |
【場所】加古川市加古川町本町三丁目 【祭神】武甕槌命・経津主命・天児屋根命・比売神 文治2年ごろ、時の雁南庄の領主、糟屋有季が奈良本宮の春日大社から分霊を迎えて建立しました。 加古川城主・糟屋武則は有季の子孫です。 境内には赤い壁が印象的な丸亀神社(通称「赤壁さん」)があります。 この赤壁には、勝負毎に強い『タマ』という名前の化猫話が伝えられており、映画化もされました。 |
日岡御陵 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町大野 被葬者は明らかではありませんが、第12代景行天皇の皇后、播磨稲日大郎姫命のお墓だといわれています。 日岡山へ葬るため遺体を乗せて印南川(加古川)を渡っていた時、 大きなつむじ風が吹いて船は転覆し、櫛と「ひれ」(天女等が背からまとっている布)だけがみつかりました。 その櫛と「ひれ」が、ご陵に葬られた為、「ひれ墓」とも呼ばれています。 |
駒の蹄と投げ松 |
|
 |
【場所】 【縁のある人】 この「投げ松」は法道仙人が一乗寺から放り投げた松と言われ神木として守られています。 |
西条古墳群 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市山手 【築造時期】5世紀初め 人塚古墳、尼塚古墳、行者塚古墳の3基を残すのみで、それぞれが国の史跡に指定されている。 出土遺物の九輪・風鐸は復元されて加古川総合文化センターで展示されています。古代ロマンを感じる空間です。 |
胴切れの地蔵 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町平野 このお地蔵さんを深く信仰していた人が、大名行列の前を横切ったために侍に斬られてしまいました。 しかし、ふと気がつくと何事もなく無事でした。 そばを見回すと、普段お参りしているお地蔵さんの胴が二つに割れ、男の身代わりとなっていました。 それ以来、このお地蔵さんを「胴切れのお地蔵さん」と呼び、一層信仰したとの事です。 今でもお地蔵さんの体にはその時の傷が残っています。 |
 |
【場所】兵庫県加古川市・高砂市 【標高】約304M 「親子で楽しむ山登り全国160」にも選定されています。 高御位山頂直下には、地元では有名なロッククライミングの練習場もあります。 初心者からロッククライマ-等の練習として大変人気のある山です。 |
日岡山公園 |
|
 |
【場所】兵庫県加古川市加古川町大野 【桜シーズン】3月下旬~4月上旬頃 わがまち加古川60選No.29です。 |